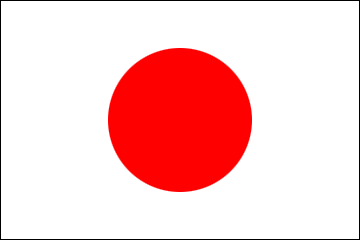野外でのダニ咬傷について
平成28年6月6日
ウクライナなどのユーラシア大陸の国々では、ダニを媒介とした感染症が現在でも発生しています。夏に向かいダニが活動する時期に入りますので、マダニ咬傷による感染症およびマダニ咬傷予防策についてご説明したいと思います。
マダニ咬傷による感染症
・ダニ媒介性脳炎(Tick-borne encephalitis, Клещевой энцефалит)
ダニ媒介性脳炎はウイルス感染症であり、大きく三種類の型に分類されます。ウクライナでは中部ヨーロッパ脳炎型に罹患する可能性が大きいようです。症状は二相性であり、第1期はインフルエンザ様の高熱が約一週間続き、解熱後2、3日してから、けいれん、運動麻痺、感覚障害などの中枢神経症状を呈するようです。死亡率は約5%ですが35%から60%の患者に後遺障害を残します。傾向として西ヨーロッパより東ヨーロッパのほうが重篤な症状を呈するようです。発症してしまってからの有効な治療法はありませんが、森林などで作業するなどマダニに刺される可能性が高い人々には予防接種が行われています。ただし、同予防接種は日本国内では薬事承認されておらず一部のトラベルクリニックでしか受けることができません。また、一年間かけて合計3回の接種が必要です。
・クリミアコンゴ出血熱(Crimean-Congo hemorrhagic fever, Геморрагическая лихорадка Крым-Конго)
媒介するダニの生息分布に一致して、アフリカ、東ヨーロッパ、中央アジア諸国で発生しています。病名からおわかりの通り、発見のきっかけは大戦中、クリミア半島に配属された赤軍兵士の間で流行したことによります。また、1950年代にコンゴで発生した同様の症状を呈した患者から同じウイルスが検出されたことにより、クリミアコンゴ出血熱と名付けられました。上述したダニ媒介性脳炎と同様にウイルス感染症であり高熱、頭痛などで発症し全身に出血班が見られます。病気に対する特効薬などはなく対症療法のみ、また、予防接種もありません。
・ライム病(Lyme disease, Болезнь Лайма)
北米、ユーラシア大陸において発生を見ます。ダニを媒介したスピロヘーターの1種ボレリアによる感染症です。ダニに刺された後、数日から数週間で特徴的な紅斑の出現とともに発熱、倦怠感、筋肉痛などが見られます。その後、病原体が全身に拡散するとともに循環器症状、中枢神経症状を呈します。治療にはテトラサイクリンなどの抗生剤が用いられます。
マダニに咬まれないようにするには?
・必要がなければ草原や繁みなどに立ち入らない。
マダニは、喘息などの増悪因子となるイエダニと異なり主に野原に生息しています。したがって、マダニに咬まれないようにするには生息地である草原に立ち入らないことがいちばん効果的な予防策となります。
・草原や繁みなどに立ち入る場合には長袖、長ズボンを着用し皮膚を露出しない。
可能ならば長靴を着用しズボンの裾を靴内に折り込むとより効果的です。
・できるならば、明るい色の服を着用する。
マダニはイエダニより大型(数mm~数cm)であるため、明るい色の服装のほうが体に付着したダニを発見しやすくなります。
・草原や繁みに立ち入った後には、すみやかに入浴するようにしましょう。
ダニは体に付着した後、すぐに吸血行動にうつらずに皮膚の吸血しやすい柔らかな場所をしばらく探し続けます。入浴、体を洗浄することにより吸血に移る前のダニを取り除くことができます。
マダニに咬まれてしまったら?
・吸血中のダニはピンセットにて頭部をつまんで取り除くようにしましょう。
虫体をつかんで取り除くと虫体内の病原菌を人間体内に押し戻す可能性があります。可能ならば医療機関を受診してください。
・草原に立ち入った後に高熱がでたり皮膚に紅斑が生じたならば、すみやかに医療機関を受診してください。
マダニ咬傷による感染症
・ダニ媒介性脳炎(Tick-borne encephalitis, Клещевой энцефалит)
ダニ媒介性脳炎はウイルス感染症であり、大きく三種類の型に分類されます。ウクライナでは中部ヨーロッパ脳炎型に罹患する可能性が大きいようです。症状は二相性であり、第1期はインフルエンザ様の高熱が約一週間続き、解熱後2、3日してから、けいれん、運動麻痺、感覚障害などの中枢神経症状を呈するようです。死亡率は約5%ですが35%から60%の患者に後遺障害を残します。傾向として西ヨーロッパより東ヨーロッパのほうが重篤な症状を呈するようです。発症してしまってからの有効な治療法はありませんが、森林などで作業するなどマダニに刺される可能性が高い人々には予防接種が行われています。ただし、同予防接種は日本国内では薬事承認されておらず一部のトラベルクリニックでしか受けることができません。また、一年間かけて合計3回の接種が必要です。
・クリミアコンゴ出血熱(Crimean-Congo hemorrhagic fever, Геморрагическая лихорадка Крым-Конго)
媒介するダニの生息分布に一致して、アフリカ、東ヨーロッパ、中央アジア諸国で発生しています。病名からおわかりの通り、発見のきっかけは大戦中、クリミア半島に配属された赤軍兵士の間で流行したことによります。また、1950年代にコンゴで発生した同様の症状を呈した患者から同じウイルスが検出されたことにより、クリミアコンゴ出血熱と名付けられました。上述したダニ媒介性脳炎と同様にウイルス感染症であり高熱、頭痛などで発症し全身に出血班が見られます。病気に対する特効薬などはなく対症療法のみ、また、予防接種もありません。
・ライム病(Lyme disease, Болезнь Лайма)
北米、ユーラシア大陸において発生を見ます。ダニを媒介したスピロヘーターの1種ボレリアによる感染症です。ダニに刺された後、数日から数週間で特徴的な紅斑の出現とともに発熱、倦怠感、筋肉痛などが見られます。その後、病原体が全身に拡散するとともに循環器症状、中枢神経症状を呈します。治療にはテトラサイクリンなどの抗生剤が用いられます。
マダニに咬まれないようにするには?
・必要がなければ草原や繁みなどに立ち入らない。
マダニは、喘息などの増悪因子となるイエダニと異なり主に野原に生息しています。したがって、マダニに咬まれないようにするには生息地である草原に立ち入らないことがいちばん効果的な予防策となります。
・草原や繁みなどに立ち入る場合には長袖、長ズボンを着用し皮膚を露出しない。
可能ならば長靴を着用しズボンの裾を靴内に折り込むとより効果的です。
・できるならば、明るい色の服を着用する。
マダニはイエダニより大型(数mm~数cm)であるため、明るい色の服装のほうが体に付着したダニを発見しやすくなります。
・草原や繁みに立ち入った後には、すみやかに入浴するようにしましょう。
ダニは体に付着した後、すぐに吸血行動にうつらずに皮膚の吸血しやすい柔らかな場所をしばらく探し続けます。入浴、体を洗浄することにより吸血に移る前のダニを取り除くことができます。
マダニに咬まれてしまったら?
・吸血中のダニはピンセットにて頭部をつまんで取り除くようにしましょう。
虫体をつかんで取り除くと虫体内の病原菌を人間体内に押し戻す可能性があります。可能ならば医療機関を受診してください。
・草原に立ち入った後に高熱がでたり皮膚に紅斑が生じたならば、すみやかに医療機関を受診してください。